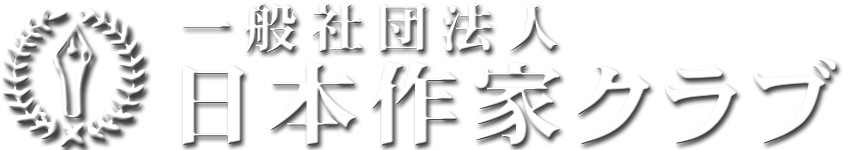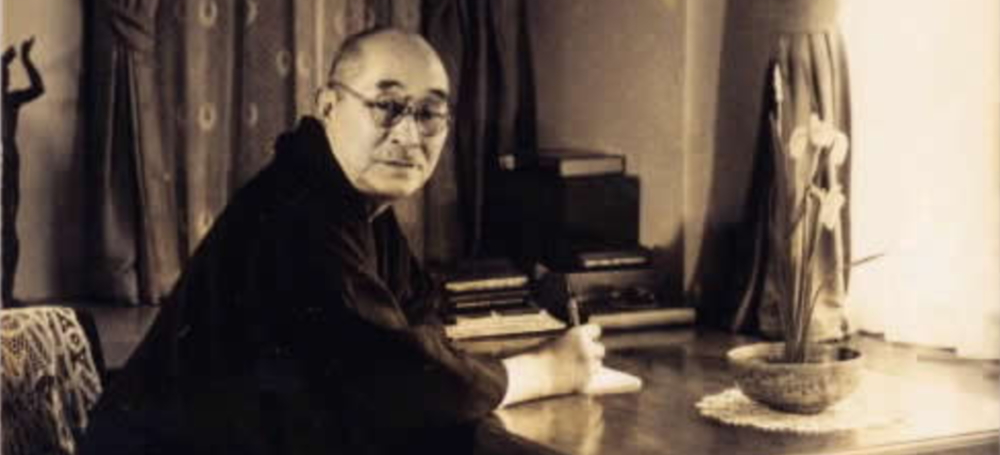
「野村胡堂文学賞」とは
About Nomura Kodo Prize
多様な顔を持つ野村胡堂のなした膨大な業績の中でも、特に捕物小説の一大傑作『銭形平次捕物控』は、江戸の下町を舞台に“岡っ引き”が活躍する国民文学として大衆を魅了し、戦前・戦後を通じて何度も映画やラジオドラマ、テレビドラマ化された。野村胡堂文学賞は、そうした胡堂の「国民的作家」の一面を顕彰する目的で、日本作家クラブが創立60周年記念事業の一環として2012年に創設した、“時代・歴史小説分野を対象にした”文学・文芸賞である。
日 時
Date and time
- 令和7年11月12日(水)
午後4時
会 場
Location
- 神田明神
住所:東京都千代田区外神田2丁目16-2
第13回 野村胡堂文学賞 受賞者ならびに受賞作品
13th Nomura Kodo Prize winners and winning works

赤神 諒 著『碧血の碑』
(小学館 2024年10月刊)
■受 賞 の 言 葉
Coffee Obsidian という隠れた名曲があります。AIが勧めてくれた曲で、ミュージシャンを含めて私もよく知らないのですが、気に入って「セ・シ・ボン」の執筆時のテーマ曲に選んでいました。でも、マイナーすぎるせいか、私のストリーム配信ではもう聞けなくなっています。
『碧血の碑』は、激動の時代に不遇の人生を歩んだ「敗れざる者たち」に着目して綴った初の短編集です。小説の形式としても、各話のシーンをあえて固定したり、季節や色やアイコンをさまざまちりばめた実験的な作品で、万華鏡を通して幕末を見るような美しさを目指していました。〈小説とアートのコラボ〉を果敢に試みた、私にとって大変思い出深い作品でもあります。
ですが、渾身の自信作もほとんど黙殺され、無念にも理解していただけず、Coffee Obsidian と似たような道を辿るんだなと寂しく思っていたころに、ノミネートいただいたのです。
敏腕編集者さんから受賞の連絡をいただいた時、私は最新作の取材で、長崎の丸山近くにおりました。早朝からぎっしり詰まったスケジュールの合間、洒落た喫茶店で一休みし、名物のミルクセーキを味わう前に写真へ収めておこうと、スマホを構えた時にぶるりと振動が伝わったのです。
私はまだ多くの読者を獲得できないまま書き続けておりますが、ありがたいことに編集者さんにだけは恵まれ、貴重なご指南を得ながら、自信作だけを世に出して参りました。
それでも私の力不足で、その多くが「隠れた名作」となってゆくのですが、こうして素晴らしい賞をいただくことで、ほんの少しずつ読んで頂く人が増えているのかなと感じております。
この度は、錚々たる方々が受賞されてきた文学賞を頂戴でき、大変光栄に存じております。
関係者の皆様に、心よりの御礼を申し上げます。
ところで、受賞連絡で舞い上がった私は、ミルクセーキの写真を取り忘れてしまいました。生まれつきのおっちょこちょいは治りませんが、受賞者の名に恥じぬよう、これからも日々、鋭意執筆して参ります。
第13回 野村胡堂文学賞受賞
赤神 諒
■赤神 諒(あかがみ りょう)氏のプロフィール

同志社大学文学部英文学科卒業。2017年『大友二階崩れ』で日経小説大賞を受賞しデビュー。
『はぐれ鴉』で大藪春彦賞、『佐渡絢爛』で日本歴史時代作家協会作品賞・本屋が選ぶ時代小説大賞、『我、演ず』で細谷正充賞を受賞。作品に『酔象の流儀』『戦神』『空貝』『誾』『火山に馳す』など多数。
■選 評
三人の予選委員によって選ばれた第一次候補作品は、赤神諒『碧血の碑』、滝沢志郎『月下美人』、高瀬乃一『梅の実るまで』の三冊。さすがは当代一流の目利きたちが選んだ作品だけに、いずれも年度を代表するにふさわしい秀作揃いでした。
この三作を作家クラブの会員投票にかけた結果、『碧血の碑』と『月下美人』の二作が選ばれました。『梅の実るまで』は、学問で身を立てようと志した青年武士が幕末の乱世を一途に生き抜こうとする感動的な教養小説(ビルドゥングス・ロマン)ですが、武芸はからっきしダメという気弱な主人公の性格設定が、チャンバラ好きの会員に敬遠されたのかもしれません。
こうして二冊に絞られた候補作の中から最後の一冊を選出するために開かれた選考会で、私は赤神氏の『碧血の碑』を推しました。これは幕末維新の激流に抗して散った「歴史の敗者」たち――新選組の沖田総司、福井藩士橋本左内、皇女和宮、横須賀造船所の技師ヴェルニー、箱館戦争の慰霊碑を守る柳川熊吉の生涯に取材した歴史ロマンの短篇集です。
いずれの作品も虚実皮膜の間に魅力的な登場人物が躍動して息もつがさず、読者はたちまち濃密な物語空間に取り込まれて主人公とともに苛烈な人生を生きることになります。その圧倒的な時空間のリアリティを支えているのは、私見によれば、学究的ともいうべき綿密な時代考証と、イメージ喚起力の強い文体です。この作者の歴史眼と文章力は『銭形平次』の作者にひけをとらないといってもいいでしょう。
滝沢氏の『月下美人』は、江戸時代後期に菜澄なる小藩の城下町で「月下美人」という女性の生理用品を開発した人々の物語。かつては剣豪として鳴らした郷士を中心に、彼の義理の娘、幼なじみの紙問屋と女医者が手を組んで、世間の白眼視に耐えながら初志を貫徹するという感涙必死の成功物語です。
私は何よりもこのテーマの斬新さに惹かれて一気に読み終えたのですが、主人公と義理の娘との微妙な父子関係、主人公と女医者との遅々として進まぬ恋愛関係の描き方に、ある種のもどかしさと物足りなさを感じました。しかし、この作家のスケールの大きな構想力とストーリーテリングの才は、将来に大きな期待を抱かせます。
『銭形平次捕物控』シリーズの作者にして捕物作家クラブ(本会の前身)の創設者でもあった野村胡堂は、報知新聞の文芸部長だった時代に、吉川英治をはじめとする多くの新鋭作家を世に送り出しました。今回もまた、その名伯楽の名にふさわしい受賞作を得たことを、会員のみなさんとともに喜びたいと思います。
野村胡堂文学賞 選考委員長
郷原 宏
■選 評
人としての感情や心情が、人を人たらしめる。これが丁寧に綴られることで、小説の登場人物には初めて血が通うのだと私は思う。
その意味で、滝沢氏の『月花美人』はまさに「人間の物語」だった。が、導入と締め括りに、同じ要素でのマイナス面がある。主人公・望月鞘音の、義理の娘への思い入れが初期段階から不自然に強い。女医・佐倉虎峰との恋愛要素も、互いの感情が醸成しないまま夫婦となったような唐突感を覚えた。とは言え、これらは本作の価値を損なうほどの難点ではない。強い引力と勢いのある文章、物語の構成や軽妙な面白さには、落選させるには惜しい魅力があった。
赤神氏の『碧血の碑』は、まず卓越した情景描写に驚愕した。一方、人物の心情面が急変しがちな点が散見される。紙面の少ない短編で心情を緻密に描くのは難しく、その弊害かも知れない。また、全編に蟷螂が登場した点が少々引っ掛かった。全てに出さずとも、一冊に通底する主題は受け取れるはずだ。
そうした中、皇女・和宮を描いた『おいやさま』は完璧な一編だった。綿密な調査の上に構築された物語は読み応え十分、和宮の心の移ろいも、徳川家茂を介在させることで無理なく潤いに満ちて伝わる。その気持ちゆえに和宮は、自分にできる数少ないこと、しかし自分にしかできないこと――徳川の歴史に幕を引く働きに身を投じ得た。無上の感銘を受ける「人間の姿」である。この一編あってこそ、本作は受賞するに相応しい。赤神氏の筆力には敬服の至りである。
選考委員 第四回野村胡堂文学賞受賞作家
吉川永青
■担当編集者より
赤神諒さんにお声掛けするに至ったきっかけは鮮明に覚えています。大藪春彦賞を受賞したと聞き購入した『はぐれ鴉』のページを何となしにめくり、目に入った冒頭の一文に痺れました──「またひとつ、血の花が咲いたらしい」。城内で人々が次々に斬りつけられているという凄惨なシーンですが、視点人物である主人公の混乱ゆえの俯瞰を感じさせつつ、残酷な赤を鮮やかに想起させる、簡潔で美しい一文だと思いました。そのまま、本篇も夢中になって読み終えました。当時、私は小学館の文芸編集室に転職してきたばかりでしたが、同じ編集部にフリーランスとして出入りしていたベテラン編集者・米田光良さんが赤神さんと交流があると聞き、紹介していただくに至りました。
初対面の席。赤神さんは朗らかかつ落ち着いた雰囲気を纏いつつも「やりたいこと、書きたいことがたくさんある!」という“逸り”が見え隠れしておられる方で、その日のうちにバラエティに富んだアイディアや構想をいくつもいただき、その中で「実はすでに一編、福井市と組んで、養浩館で榎本孝明さんに朗読していただく予定の短編があるのですが、もしご興味があれば」といただいたのが「蛟竜逝キテ」の原稿でした。拝読すれば、これもまた冒頭「されば、御免!」と言い放つや池に飛び込む橋本左内のキャラクターに一気に引き込まれ、読み進めれば、左内と福井藩主・松平慶永の静かで前向きな交流が心地よい一編。それを元に、同じ志のもと育まれていく二人の友情と、それゆえの結末の切なさをさらに読者に訴えかけられるよう推敲をしていただいたものを、WEB文芸誌「STORY BOX」に掲載することになりました。
さて、「蛟竜逝キテ」には推敲時に少し頭を悩ませた縛りがありました──前述したような朗読会を前提にした作品でしたので、全篇を会場である養浩館で展開する必要があったのです。しかし、この短編を今後一冊の本にすることを見据えるにあたり、赤神さんはその制約すらポジティブに、テーマとして活かしてしまいました。こうして、教科書には多く語られない幕末の“敗者”たちの強い想いが残る“場所”を舞台にした物語たちが、誕生することとなりました。
その後いただいた構成プロットからは、令和という時代が驚くほど幕末に重なる部分があるということも気付かされました。国際交流が進み、情報革命が起こり、既得権が崩壊した転換期。グローバル化と多様性が広がる混乱の中で、ゆるぎ始めた自分の軸を改めて模索しなければならない。「セ・シ・ボン」で描かれる小栗上野介とフランス人技師ヴェルニーの国際交流、「七分咲き」での沖田総司の恋愛模様、どの話も歴史時代小説でありながら現代的な要素がおおいに含まれています。収録作はすべて、原稿のやりとりを重ねた思い入れのある話であるものの、個人的な“推し”を挙げるとすれば、大奥の終焉を和宮と天璋院の視点から描いた「おいやさま」。大奥と言えば女同士の苛烈などろどろバトル、という固定観念を清々しく壊してくれます。いや、最初の方は確かに、そのようなこともありつつも……大きな危機を前にした団結は、似た境遇の女性同士だからこそ、深い思いやりと強い覚悟にあふれています。これも今のムーブメントに通ずるものがあり、作業中、何度目頭を熱くしたことか。
三条大橋、養浩館、江戸城、横須賀造船所、碧血碑……作品の舞台となっている“場所”は、すべて現存しており、実際に足を運ぶことができます。遠いようで近い幕末を感じられる場所として、作品の読後にでも訪れてみるのも一興です。
そして、この度『碧血の碑』が野村胡堂文学賞を受賞し、“銭形平次の碑”を晴れやかな気持ちで訪れることが出来ること、心より嬉しく、感謝いたします。赤神さん、おめでとうございます。
赤神 諒著『碧血の碑』担当編集者
富岡 薫(とみおか・かおる)
選考会 & 授賞式
Commemorative photos
「野村胡堂文学賞」協賛法人・団体
OFFICIAL SPONSORS

株式会社 ファミリーマート

江戸総鎮守 神田明神